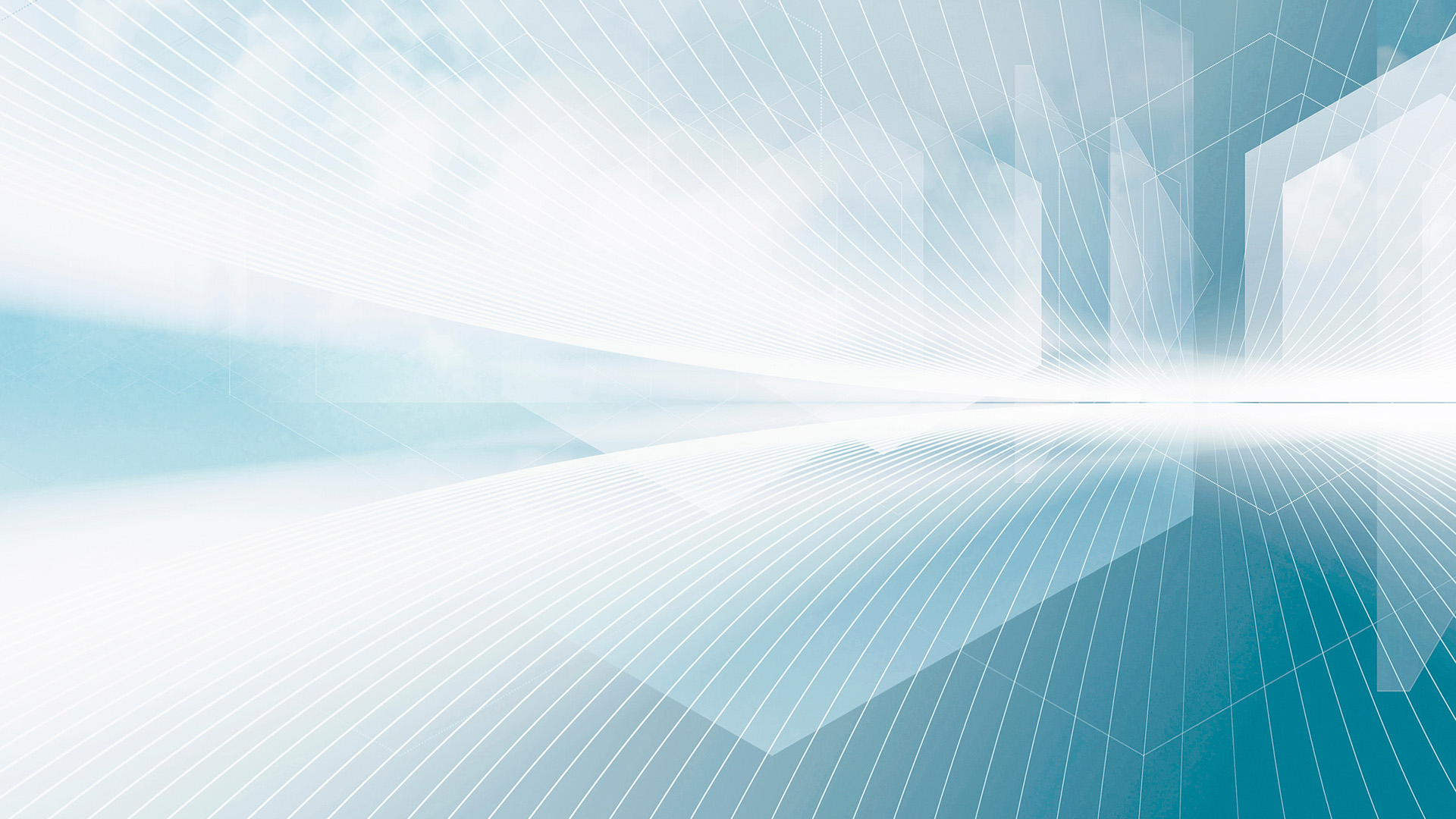
前回のコラムの中は、事業承継の信託における活用についてご案内いたしました。今回のコラムでは、資産承継の場面で信託を活用するケースについてお伝えします。
資産承継の手法として、最も一般的な手法は遺言です。遺言を作成することで、ご自身の死後、財産を誰に承継してもらうのか、生前にご自身の意思で決めることができます。
ご自身の相続開始時に遺言の効力が生じ、遺産の所有権が相続人、受遺者に移転します。一方で、資産承継の場面では、相続開始前に、資産の名義変更を必要とするケースがあります。例えば、事業用の資産を所有しているケースです。後継者に事業承継を行った後、当該資産の所有権も本来であれば、後継者に移転したいと考えます。もっとも、所有権を移転するにあたって、贈与税や所得税等の納税のコストを考える必要があります。納税コストの負担を考えると、後継者への事業用資産の移転が困難なケースもあります。
現所有者がご健康で、事業用資産の管理に問題がない状況であれば、特に困る事は無いかもしれません。しかし、認知症など判断能力が低下した際、ご自身の能力の低下が事業に影響与えてしまう可能性が残ります。判断能力が低下した場合、賃貸借契約などの法律行為を適切に行うことができなくなってしまうからです。
民事信託を設定することにより、前述した事業に対するマイナスの影響を防ぐことができます。例えば、委託者は現所有者、受託者は後継者、受益者も現所有者の自益信託を設定します。信託財産は、事業用に用いている不動産などです。この信託を組成することによって、事業用資産の名義上の所有者を後継者に移すことができます。ただし、実質的な経済的利益を受ける権利など受益権は現所有者の手元に残ります。このスキームを用いる場合、受託者となる後継者に事業用財産の管理権限を与えることができますが、事業用財産を贈与したり、売却したときのような納税コストは生じません。つまり、後継者への事業承継と合わせて、事業用資産の承継をスムーズに行うことができます。
それに加えて、現所有者の死亡を信託の終了事由として、設定することによって、現所有者から遺贈を受ける時と同じような形で、後継者に事業用資産を引き継がせることができます。
このような民事信託のスキームは、認知症対策のスキームとして幅広く使われています。ご自身が認知症になってしまうと判断能力が低下し所有されている資産の塩漬けが生じてしまいます。民事信託を行い、早期に次世代に資産の管理を承継させることによって、資産の活用が不十分になるといった事態を予防することができます。
以上のように、民事信託による資産承継を行うことで、遺言よりも早期に資産の管理権限の承継を進めることできます。
2回にわたって信託を用いるケースについてご案内してきました。次回以降は、信託の制度のご説明をさせていただこうと考えています。
以上
この記事の執筆者




